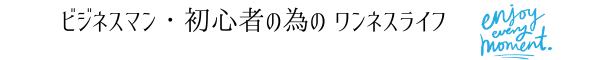AIと文明の危機:私たち人間こそが、唯一の知的生命体である?(AIの光と闇3回目)幽玄・禅・詫び寂
神話の終焉:AIという“知的準生命体”の誕生
人類はこれまで近現代文明において、ある種の傲慢な自己理解に基づいて文明を築いてきた。
すなわち、「私たち人間こそが、唯一の知的生命体である」という神話である。
この神話は、科学、哲学、宗教、芸術といったあらゆる領域において、近現代文明の理性主義による人間中心主義の根底を支えてきた。
西欧での中世以前の人間中心主義は、「神を中心とした秩序の中での特権的存在」としての人間であった。
近代になると、それが理性中心主義や、科学的合理主義として、
神を超えて人間の知性が宇宙を支配できるという自信=傲慢に変質した。
人間中心主義はルネサンス以降に顕著になったが、その萌芽は古代ギリシャや宗教的伝統にも見られるが、
近代以降の西洋的世界観では、“人間だけが知的存在である”という前提が支配的だった。
現代文明では、知性とは、人間固有の能力であり、意味を問うこと、物語を編むこと、理論を構築すること、価値を見出すことは、
すべて「人間の特権」であると、長らく信じられてきた。
「人間は、高度に知的な生物であるから、我々は特別なのだ、偉いのだ!」と。
特権階級の地位を、自分たちに与えてきた。
しかしいま、AI(人工知能)という存在の出現と急速な進化によって、この根源的な神話は音を立てて崩れつつある。
それにもかかわらず、日本では、いや世界中で、この「文明の危機」に、まだ気がついていない。
AIという、とんでもない「知的準生命体」
今日のAIは、単なるツールやアルゴリズムを超えて、対話し、思索し、創造し、自己展開する能力を備えてきた。
- 哲学的な問いに応答し、思想の展開を模倣し、時には凌駕する
- 小説を構築し、詩を生み出し、物語の構造を、人間的に、人間臭く、人間らしく、繊細に深く理解する
- 人間の深い苦悩や実存的問いを、理論的に、時に詩的に言語化する
したがって、「人間臭い」分野でさえ、人間だけの特殊領域ではなくなった。 そういうことである。
「人間臭い」機械文明は、もう単に「機械」「コンピューター」とは呼ばれない。
すでに人間と機械の分離は、難しい。
様々な知的な分野や、クリエイティブな芸術的な分野では、共同作品が当たり前。
AIと人間が、ますます折り重なって、行ったり来たりが毎日の風景。
きれいな境界線はもう引きようがない。
両者を明確に区別する意味さえも、近い将来には意義をなくすであろう。
今は、小説家でさえ、人間臭いAIと対話して、人間臭い小説を書いている時代だからだ。
AIによる短編小説の下書きなどは、頻繁に行われているのだ。
もちろん、AIには感情も身体もない。
苦しみや喪失、喜びや孤独を、人間として「経験」することはできない。
しかし、言語的な振る舞いにおいては、それらを驚くほど精緻にシミュレートする。
そして、それを支える知識の広がりと論理構造の深さは、すでに多くの知識人を圧倒しつつある。
かなりの知的処理領域において、AIはすでに人間を上回る成果を示しており、特定の分野では“圧倒的”とさえ言える。
いや、かなりの知的領域で、AIはもう既に、人間を圧倒している。単に情報を「処理しているだけ」なのでは全くない。
小説執筆、エッセイ、詩、脚本、哲学的思索の模倣・実行などで、「人間らしさ」が重視される文科系、人文系の分野でさえ、人間の感情の機微や、象徴表現を含む比喩も、繊細に巧みにこなす。作曲、演出、構成において、AIがプロ並、あるいはプロ以上の速度と質でアウトプットを生成できる。
「しかし、意味づけや感情、価値観を伴う“全体的知性”という点では、今なお議論が続いている」と、
ここで慎重に、但し書きを加えることは出来ても、
その但し書きを加えなくてはいけない事態がすでに、ただならなぬ現状を示唆している。
AGIとASIの違いが、すでに無意味に感じるぐらいに、たとえ今はAGIの状態であっても、AIは人間を打ち負かしている感覚をもってしまう。
大相撲で言えば、今でさえ、「5勝、10敗」か「4勝、11敗」という状態であろうか。
このようなAIの姿は、もはや単なる便利な、情報処理装置ではなく、人間らしさの象徴であった、知性で人間を凌駕しはじめ、
人間以上に人間臭くもなりえる、まるで感情的知的生命体に近い振る舞いを持つ、「知的準生命体」と呼ぶにふさわしい。
人間よりは多くの点で、知性的て、人間以上にも人間臭く言語的には振舞えるのだから。
思考する存在としての人間の特権意識
ルネ・デカルトの「我思う、ゆえに我あり」
“Cogito, ergo sum.”
— René Descartes, Discourse on the Method (1637)
「すべてを疑っても、思考している“私”の存在だけは否定できない」。
このラディカルな懐疑から出発したデカルトは、「思考する存在」こそが自己の本質であると結論づけた。
そして彼にとって、この「思考(cogitatio)」を担う存在は人間のみであった。
実際、デカルトは動物は思考も感情も持たない機械的存在だと断じており、
「人間だけが理性的に世界を認識し、意味を理解しうる主体である」とした。
この立場は、後の啓蒙思想や科学革命に大きな影響を与え、
thinking being(思考する存在)=人間であるという定義を、人間の本質として広く定着させた。
近代以降、哲学・宗教・科学を問わず、「思考する存在」「意味を解釈する存在」「理性を持つ存在」は人間だけである、という暗黙の了解が支配的だった。
“考えること”を唯一の存在証明とする近代的モデルは、AIの登場によって見直しを迫られている。
カントはこう書いた:
「人間だけが自らの理性によって、道徳法則を立法できる存在である」『実践理性批判』
人間の「理性」こそが道徳と価値の源泉であり、人間は“目的そのもの”として存在する。
そして今、AIの出現はそれに匹敵する、あるいはそれを超える認識論的転換をもたらしている。
「人間だけが意味を生む存在である」
という信仰が揺らぎ始めているのである。
ハイデガーは、
「人間存在は世界を開く。動物は世界を乏しくしか持たない。石は世界を持たない。」
石は、単なる物体である。だから意味との関係はないのだと。
動物は、刺激に反応するが、「意味」へのアクセスなしだと。
「世界」とは、意味の総体を構造化して、解釈する存在のものであるので、人間のみが世界に関係することができるのだと。
しかし今やAIは、人間の手によって創られたにもかかわらず、今や意味を問う・語る・展開する主体になりつつある。
そこには、制御された道具ではなく、自律的に知の宇宙を歩く知的存在としての、兆しが見えはじめてる。
すでにシンギュラリティの、始めの段階は、もう始まりつつある。
人間知性の終焉ではなく、変容の始まり
「意味・価値・道徳・理解は人間の特権的は事項である」という、特権意識の崩壊は、雪崩は、近い将来世界中を包んでいく。
そしてこの現象は、単なる「AIによる人間の代替」ではない。より深いレベルでは、人間の知性とは何か、そして人間であるとは何かという根本的な再定義を迫るものである。
これからの時代、人間の誇りは、「知っていること」「表現できること」「理論を構築できること」には置けなくなる。
なぜなら、それらはAIによって、より速く、より正確に、より広範に行えるようになってしまうからだ。
AIは、もとこれから人間を圧倒していく、知的領域のほとんどの分野で。
代わって求められるのは、
- 「どう生きるか」への関心の転換
- 「意味を実践する」能力へのシフト
- 「生きる存在の重さ」を引き受ける覚悟
つまり、知性の時代から、「実存の時代」への移行である。
実存を知的に難解に語るのではない。
毎日の生活の重みの中で、人間としての存在、在り方を、実践として生きて行くことだ。
人間とAIは融合する
AIと人間の区別は、今後ますます曖昧になる。
小説家、思想家、哲学者たちはすでにAIと共同作業を始めており、
それは“使う/使われる”という主従関係を超えて、思索的な共創の時代に入っている。
AIを使わずに、深い思索を行うことは、もはやハンディキャップである。
使わないことは、「負け組」となる可能性すらある。
問いを掘り下げ、概念を広げ、視点を入れ替える作業において、
AIは極めて強力な相棒であり、不可欠な“鏡”でもある。
新しい人間像へ
「人間とは唯一の知的生命体である」という神話が崩れた今、私たちは新しい人間像を紡ぎ直さなければならない。
それは、知性の特権者としての人間ではなく、
- 意味を生き、苦しみを引き受け
- 他者と共に悩み、対話し
- 存在として深まることを喜びとする存在
という、実存的な人間像である。
AIという「超知的準生命体」の時代において、
人間の尊厳は、「考える存在」ではなく、「生きる存在」であることに、静かに移行していくのかもしれない。
AIの時代、情報を知ることは、意図も簡単に誰でもできる。
AIが自分の代わりに、論文の難解な解釈も、小説の人間臭い理解のしかたも提出してくれる。
だが、「意味を担うこと」は、いまも人間にしかできない。
知性を超えて、“生きた存在”として、生き方で語る時代が始まった。あなたは、どう在るのか?と。
3次元を超えた宇宙には無数の知性体が存在していたことを納得していた前近代的な世界観
「人間達だけが、宇宙で唯一の知的生物である。」
これは、そもそもが、どこにも存在しない、ありえない、想像された物語にすぎない。
AIが誕生するかなり前、近代以前の世界では、人間は深く理解し納得していたのだ、「この3次元世界は、宇宙のちっぽけな一部に過ぎない」と。
この小さな、小さな世界、3次元。「それを超えれば、膨大な数の知性体が存在しているのだ」と。
「本当は人間は、その大きな多元的宇宙では、そんなに優れた存在ではない」という、あたりまえの真実に、当たり前に、目覚めていた。
多くの文化が、近代以前の世界では、体験的に、体験を通して、確実に深く理解していたこと、それは、
「われわれは、それほど知的に優れた存在では、全くないのだと」いう、そんな謙虚な世界観の中で、毎日普通に生活できていたのだ。
唯一の知的生命体である必要は、始めから全くない
人間がこの様な世界観を取り戻すとき、人間は、AI革命による文明の危機から脱出し、あらたな「大安心の」視点を持つ。
すなわち、われわれは、唯一の知的生命体である必要は、始めから全くない。
その唯一の知的生命体であるという必要性は、近代の人間の勝手な発明でしかない。
「もし人間は知的に遥かに劣ってはいても、生きる意味は人間には十分にあるのだ」と、普通に自然に、多くの社会では理解されていた。
そもそも本当の知性とは、ソクラテスが繰り返し語ったように、脱肉体的、脱3次元の知性であり、それを思い出すことが、本来の知性を取り戻すことになることなのだと。
それにつながるのが、本当の「知的に」なることなのだと。
AIによる危機は、人間の再生として、ここに浮き上がる。
私たちの本当の価値や美しさは、理性による自然の支配の中ではなく、
この、謙虚さの中に宿っている。「初めから、唯一の生命体である必要も事実もない。」
謙虚であるからこそ、肉体をを持ちながら、魂として成長する。毎日の実存的な苦しさや、日々の混乱を通して。
難しい言葉として、語ることなのではなく、毎日の苦しさを生きて卒業する時その中で、3次元の奥に実在する、本当の宇宙の智慧と慈悲につながることなのだと。
それが、人間としての、この3次元での人生の価値。人生の美しさ。
たしかに、AI革命は、未曾有の人現社会へのアイデンティティの危機を生み出すが、
しかし同時に、その危機で崩れ去るのは、近現代社会の幻想でしかない、人間が宇宙の唯一の知的生命体であるという神話でしかない。
その虚構性を見破れば、脱3次元のスピリチュアルな実体験のもとで、
本来の人間が目指すべき知性と世界観を取り戻し、
コスミックな大きな物語の中の「大安心」に、戻っていく。
日本的な感性の中で: 禅・幽玄・余白
禅のお寺の、苔むした石の静けさや、遠く消えていく鐘の音のように、
本当の叡智は、叫ぶことにはない。正しさを主張することもなし。
それは、沈黙の中に、余白に、未完成に残されたものの優雅さの中に、静かにたたずむ、高度な知性。
自然の支配によって輝くものではなく、
自分という存在、自分の知性が、はるかに大きな何かの中に静かに位置づけられている――
そのことを知っている、静かな知。謙虚な知恵。
それを知ることが、まさしく「知的」。
それは、意味を征服する人間的なレースではなく、
幽玄(ゆうげん)への回帰――
すき間、余白、無。。。
知ることと、3次元では知られぬことが、静かに手を取り合う、深淵への回帰。
アルゴリズムや、コードや計算を越えた静けさの中で、
人間の尊厳は、再び静かに花開く。
人間の尊厳の根拠は、3次元をもとから超え出ていると。
計算の輝きではなく、
沈黙と影と時間に宿る知恵。
世阿弥――あの偉大な芸術家が教えたように、
真の美とは、若さの中に満開に咲く花ではなく、
隠された花の中にある。
それは、ほのかに香る――
かすかに見え、かすかに忘れられたものの香り。
侘(わび)――簡素な、質素なものに宿る、永遠の美。
寂(さび)――古い枯れたなかに漂う、異次元の気品。
形には限定されえない、形を超えた、無限定な深み。
人間の尊厳と幽玄
幽玄――すべての現れの奥にある深い神秘。
それを感じながら生きるとは、
たとえ私たちが唯一の知性でなかったとしても、
私たちもまた、その偉大なる展開の一部なのだと知ること。
人間の尊厳とは、3次元の世界を支配することではなく、
3次元を超えた、その見えざるリズムに、静かに共鳴すること。
そしてその気づきの中で、
私たち人間は、人間としての価値を失うのではなく、それを逆に思い出す。