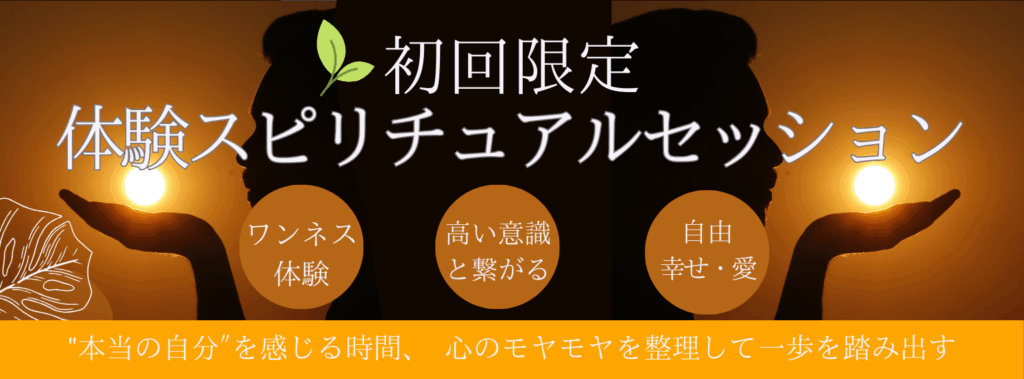天皇は仏教徒だった?──知られざる日本史 天皇と仏教の深い関わり
はじめに 門跡寺院に見る多様な信仰の伝統
現代の日本では「天皇=神道の象徴」というイメージが広く浸透していますし、神道と聞けば伊勢神宮や天照大神がすぐに思い浮かぶ方も多いでしょう。
「天皇は神道の象徴」というイメージは、現代の日本人にとってごく当たり前のように思えるかもしれません。
けれど歴史を振り返れば、その姿はもっと複雑で、多様でした。
実際には、神道だけではなく、天皇や皇族が仏門(仏教)に入り、熱心に仏教に身を捧げ、
仏教の僧侶として生涯を送ることも少なくありませんでした。
その象徴的な存在が「門跡寺院(もんぜきじいん)」(仏教のお寺)です。
今回は、天皇と門跡寺院や京都の禅のお寺の関係に焦点をあてながら、「神道は純粋なものでは全くなく、混ざり合いの上に豊かに成り立っていた」という視点を深めてみたいと思います。
天皇や皇族は神道の祭祀者であると同時に、仏教や陰陽道などほかの多くの信仰を熱心に受け入れて実践してきました。
つまり―― 神道とは本来、多重信仰(多元信仰)そのものだったのです。
(この記事は、noteのに出した記事を詳しくしたものです: https://note.com/muratawisdom/n/n651c3bf8ae01 )
門跡寺院とは何か
門跡寺院(お寺の種類のひとつ)とは、皇族や摂関家の子弟が、住職を務めた特別な仏教のお寺を指します。
「門跡」とは本来「御門の跡」、すなわち天皇の宮中に近い高貴な血筋の人が住持したお寺という意味です。
そのため門跡寺院は単なる仏教の施設ではなく、皇室と仏教が密接に交わる象徴的な場でした。
皇族が仏教徒として、出家し、仏教の僧侶として修行し、仏教の寺の住職となることは、
宮廷文化の中では決して特別ではなく、むしろ伝統的なよくある選択肢の一つだったのです。
ですから天皇や天皇家は、熱心な仏教であったのです。
現在のイメージでは、天皇は神道だけを信仰するイメージになっていますが、それはごく最近に作られたものに過ぎません。
皇族が住職を務めた代表的な門跡寺院
仁和寺(にんなじ)
仁和寺は宇多天皇(867–931)が建立した仏教のお寺、のちに「御室御所(おむろごしょ)」と呼ばれました。
歴代の門跡には皇子や親王が多く任じられ、天皇の血を引く僧侶がこの仏教のお寺の住職を務める寺として知られています。
現在でも「御室桜」で有名ですが、その背後には「皇族が寺を守り、仏教を実践してきた歴史」が流れています。
青蓮院(しょうれんいん)
青蓮院に残る皇族修行の記録は、「天皇=神道のみ」という近代的イメージが歴史の実像とズレていることを、静かに物語っています。比叡山延暦寺の三門跡の一つとされ、代々皇族がこの仏教のお寺の住職となりました。
宮中と仏門の境界がいかに緩やかであったかを物語っています。
門跡寺院は、単なる寺ではなく「宮廷文化と仏教が交わる場」であり、天皇や皇族がいかに仏教に深く関わっていたかを示す象徴。
青蓮院は、京都の知恩院の隣に位置し、市内中心部からも訪れやすい寺です。僕自身が大好きなお寺ですが、比叡山延暦寺の三門跡のひとつとして、代々皇族が住職を務めました。
特に重要なのは、後桜町天皇(在位1762–1770・女性天皇)がここで修行したという記録です。
天皇が僧侶と同じように修行を行ったという事実は、現代の私たちのイメージからすれば驚きでしょう。
青蓮院はまた、比叡山の末寺として「王権を守る祈りの場」の役割も果たしました。
庭園や伽藍に漂う静けさの裏には、天皇家と仏教が一体化して国家を祈りで支えた歴史が刻まれているのです。
青蓮院に残る皇族修行の記録は、「天皇=神道のみ」という近代的イメージが歴史の実像と大きくズレていることを、静かに物語っています。
大覚寺(だいかくじ)
嵯峨天皇の離宮を寺に改めたのが起源です。
以後、皇族が門跡として代々住持を務め、「嵯峨御流」という華道の流派もここから発展しました。
単なる寺院ではなく、文化芸術の発信地としても大きな役割を果たしたのです。
三千院(さんぜんいん)・曼殊院(まんしゅいん)
これらもまた天台宗の門跡寺院で、皇族や摂関家の子弟が住持しました。
京都の奥座敷のような地にあり、庶民の信仰と貴族・皇族の精神世界をつなぐ場でもありました。
この様に天皇や皇族は、仏教を自らの信仰生活に深く取り入れていたのです。
門跡寺院の役割と意味
門跡寺院という仏教の寺は、単なる皇族の出家先ではありませんでした。
そこは 政治・文化・信仰の交差点であり、国家の安定と人々の心をつなぐ大きな役割を担っていたのです。
第一に、門跡寺院(仏教のお寺)は「王権の祈りの場」でした。
天皇家の血を引く僧侶が祈ることで、仏教の加護が国家全体を覆うと考えられました。
そこでは「仏の力」と「王権」が一体となり、国を守る精神的基盤が築かれていたのです。
第二に、門跡寺院は文化の発信地でもありました。
仁和寺からは御室流の華道が、大覚寺からは嵯峨御流の書や絵画が広がりました。
皇族が住職を務めたからこそ、仏教寺院が宮廷文化と深くつながり、芸術や学問が花開いたのです。
第三に、門跡寺院は「多重信仰の象徴」でした。
宮中では神道系の神祇祭祀が続けられ、同時に門跡寺院では皇族が仏教を実践する。
この二つは矛盾せず、むしろ相互補完しながら共存していました。
つまり天皇家が神道だけを実践していたのではなく、むしろ「神道と仏教の間に大きな橋をかけた存在」であり、
日本文化の「調和と混ざり合い」を体現する存在だったのです。
南禅寺・大徳寺・妙心寺──門跡ではないが皇族と文化的に交わった禅の寺
-
南禅寺――「皇室創建」の別格大本山(門跡ではないが皇室ゆかりのお寺)
-
大徳寺――宮廷文化と交わった禅の拠点(門跡ではないが皇室ゆかりのお寺)
-
妙心寺――皇室の強い庇護を受けた大本山(門跡ではないが皇室ゆかりのお寺)
南禅寺──皇族が創建した禅の大寺
鎌倉時代、亀山上皇は自らの離宮を禅寺に改め、南禅寺を創建しました。これによって、南禅寺は「皇族による創建」という歴史をもつ大寺院となりました。
南禅寺は臨済宗の大本山として発展し、皇族や公家の文化とも結びついていきました。
いま観光地として有名な水路閣や庭園も、そうした「皇族と禅の文化交流」の延長線上にあります。
① 創建の由来:亀山上皇の離宮から誕生
南禅寺は鎌倉時代末期、亀山上皇(1249–1305) が自らの離宮を禅寺に改めたことに始まります。
その際、無関普門(むかんふもん)という中国・宋から渡来した禅僧を開山に迎えました。
つまり南禅寺は「皇室の離宮を母体とする禅寺」であり、創建の時点から皇室との関係が極めて濃厚です。
② 「別格」の寺格──日本禅宗の最高位
南禅寺は臨済宗の大本山ですが、単なる大本山ではありません。
室町時代以降、五山制度(禅宗寺院の格付け)の頂点に位置づけられ、さらに「別格」とされました。これは「皇室創建の禅寺」であることが大きな理由で、寺格的にも他の禅寺より高い扱いを受けたのです。
つまり、南禅寺は「皇室ゆかりの禅寺」として特別な地位にありました。
③ 皇室の祈りの場としての役割
南禅寺は、歴代天皇の追善法要や国家安泰を祈る場としても用いられました。
特に南北朝時代から室町期にかけては、皇室と公家社会が禅文化に接近し、南禅寺はその拠点のひとつになりました。
④ 文化面での皇室との関わり
南禅寺は庭園・建築・書画などの文化芸術でも有名で、これらは宮廷文化と深く響き合っています。
たとえば有名な「虎の子渡し(虎渓橋図)」などの絵画や、枯山水庭園は、皇族・公家が好んで交流した文化空間でした。
大徳寺
足利義満の庇護を受けて発展した臨済宗の大寺院。皇族との直接的な「門跡関係」こそありませんが、宮廷文化や茶道(千利休)を通して皇室とも交流しました。大徳寺の法要や文化行事には、しばしば皇族や公家が関わっています。
大徳寺は臨済宗大徳寺派の本山で、京都の北区紫野に位置する禅寺です。鎌倉時代末期の正和4年(1315年)、大燈国師・宗峰妙超によって創建されました。禅宗の厳格な修行道場として知られ、戦国時代から桃山時代にかけて大きな影響力を持ちました。
皇室との関係で特に注目されるのは、次のような点です。
① 足利義満と大徳寺、そして後小松天皇
大徳寺は一時衰退しますが、室町幕府三代将軍・足利義満の帰依を受けて再興しました。義満は後小松天皇(在位1382–1412)とも深く関わり、義満の政治力を背景に大徳寺は皇室や公家社会と文化的なつながりを持つようになります。義満自身が北山に建立した金閣寺(鹿苑寺)も、禅の美意識と宮廷文化が融合した場でした。
② 皇室と大徳寺の文化交流
大徳寺は単なる禅の修行道場ではなく、茶道・書院造・絵画といった文化芸術の拠点として発展しました。その文化的営みには、しばしば皇族や公家が参加しました。
たとえば大徳寺の法要や重要な行事には、宮廷からの勅使が派遣され、天皇や皇族が儀礼的に関与することがありました。これによって「禅」と「宮廷文化」の交差点としての役割を果たしたのです。
③ 皇室と茶道を媒介としたつながり
大徳寺といえば、千利休をはじめとする茶人との深い結びつきで知られます。茶道は単なる嗜みではなく、当時の権力者や皇室との交流の場でもありました。大徳寺の高僧たちは茶道の精神的支柱となり、その茶会にはしばしば公家や皇族が加わりました。ここに「皇室と大徳寺の文化的交流」の姿が見て取れます。
④ 大徳寺の皇室への祈り
また、大徳寺は臨済宗の寺として「国家安泰」「皇室安泰」を祈る法要を行ってきました。門跡寺院のように皇族が住職を務めることはなかったものの、「天皇家を祈りの対象とする場」としては確かに機能していたのです。
妙心寺
後花園天皇の時代に強く庇護された臨済宗の寺。こちらも門跡寺院ではありませんが、皇室が禅宗を精神文化の一部として支えた歴史を示す例といえます。
門跡寺院と「皇族ゆかりの大寺院」の違い
歴史をたどると、天皇や皇族と深いつながりを持つ寺院は大きく二種類に分けられます。
① 門跡寺院
門跡(もんぜき)とは、本来「御門の跡」、すなわち皇族や摂関家の子弟が住職を務めた寺を指します。
上にあげた、仁和寺・青蓮院・大覚寺・三千院・曼殊院などが代表的で、歴代の門跡は皇子や親王が務めました。
つまり「皇族自身が仏教僧として修行し、寺を治める」ことが制度化されていたのです。
ここには「天皇や皇族が熱心に仏教を生きた」という事実が色濃く刻まれています。
② 皇族ゆかりの大寺院
一方で、必ずしも門跡ではなくとも、皇室との関わりが深い大寺院も数多く存在します。
例えば、南禅寺は亀山上皇の離宮を改めて創建されたものであり、大徳寺や妙心寺も室町期に皇室から厚い保護を受けました。これらは「皇族が直接住職になったわけではない」が、「皇室の庇護によって発展した寺院」なのです。
この二つは同じく「皇室と仏教の近さ」を示すものですが、性格が異なります。
-
門跡寺院: 皇族そのものが仏教を実践し、寺を治めた。 皇族・摂関家が代々住職(=皇族が直接、仏教を生きた場)
-
皇族ゆかりの大寺院: 皇族が創建・保護し、仏教を支えた
いずれにしても共通しているのは、天皇家は決して神道だけを信仰していたのではなく、仏教を深く支え、生きた存在であったという点です。
天皇と仏教の近さ
門跡寺院の存在は、「天皇=神道だけ」という固定的なイメージが、いかに近代的な産物であるかを示しています。
天皇の子や孫が僧侶になることは珍しくなく、むしろ自然な選択肢でした。
神道の祭祀を行いながら、同時に仏門に入り、仏教儀礼を実践する。
それは矛盾ではなく、むしろ「自然で当然」という感覚でした。
つまり天皇や皇族にとって、神道と仏教は対立するものではなく、共に生きる二つの呼吸だったのです。
庶民の信仰との響き合い
庶民の暮らしを見ても、この多重信仰(多宗教)の姿勢は共通しています。
人々は自分の土地の神や祖先神を祀り、寺で祈り、必要があれば陰陽師に祈祷を頼む。
庶民にとって「信仰は選択制」ではなく、「すべてを受け入れる柔らかさ」でした。
だからこそ、皇族が仏門(仏教)に入っても不自然ではなく、むしろ人々の生活感覚と響き合っていたのです。
その上、天皇は仏教の他にも、陰陽道や、道教や、山岳信仰などのエキスパートでもあり、様々な宗教を熱心に実践してきた、多重信仰の実践者です。
ですから決して純粋に「神道だけ」を実践し信仰してきたのではありません。
それは、ごくごく最近の話でしかありません。
長い間にわたり「多宗教的」な、柔軟でフレキシブルな生活を送っていました。
「純粋神道」という近代の幻想
ではなぜ、現代では「天皇=神道の象徴」というイメージが定着したのでしょうか。
その答えは、明治期に作られた国家神道にあります。
明治政府は、西洋的な「国民国家」をつくるためにキリスト教的な宗教の、制度化を進めました。
明治政府は欧米の国民国家を視察する中で、キリスト教が国民統合の精神的基盤として機能している姿に注目しました。その発想を神道に転用し、本来は宗教以前の多様性だった神道を、国家のための倫理・儀礼として再設計したのです。
その際、天皇を国家統合の中心に据えるため、地域に広がっていた神道の多様な信仰を排除し、
「天皇=神道」という日本にはそれまで存在しなかった、単線的なイメージを国民に強制したのです。
門跡寺院が象徴するように、実際には皇族自身が仏教徒でもあり、庶民も複数の信仰を同時に生きていました。
しかし近代国家は、それを「不純」「混ざりもの」として切り捨て、「純粋な神道」を新たに作り上げました。
皮肉なことに、「純粋神道」という考えは、日本の伝統を守るどころか、
本来の多様性と柔軟さを奪うものだったといえるでしょう。
おわりに─ 天皇は熱心な「仏教徒でもあった」─ 忘れてはならない逆説
「天皇は神道の象徴」という言葉は、現代の常識のように語られます。
けれど歴史が教えるのは、むしろ真逆です。
天皇や皇族は、神道の祭祀を担う一方で、仏教を篤く信仰し、仏教の僧侶として生涯を送ることもありました。
仁和寺や青蓮院、大覚寺、三千院、曼殊院……それら門跡寺院の歴史が物語っているのは、天皇は神道だけではなく、仏教徒でもあったという事実です。
その上、陰陽道や道教などのエキスパートでもありました。
明治以前の長い長い歴史の中では、純粋な神道という「独立した姿」があったのではなく、最初から混ざり合いの信仰しか存在しなかった。
それが日本文化のであり続けました。
にもかかわらず、明治以降の国家は「純粋な神道」という近代的な幻想を掲げ、それを「日本の伝統」と言い換えました。
明治政府は大久保利通などを中心に、キリスト教的な「国教モデル」を参考に、神道を人工的に制度化しました。
その結果、「神道だけを信仰する天皇」という近代的イメージが国民に植え付けられたのです。
保守派の一部は今もなお「純粋な神道の回復」を唱えますが、その発想自体がすでに西洋的な宗教モデルの輸入品であり、歴史の事実とは矛盾しています。
門跡寺院の歴史は、静かにこう語りかけています。
本来の日本の精神は「純粋」ではなく「共生」。
排他ではなく、受容。
単一ではなく、多様。
それを忘れると、私たちは日本文化の根を見失うことになります。
独立した神道だけの神道などは元々存在せず、様々な宗教(仏教・陰陽道・道教など)を豊かに内包した状態、
「多宗教状態」こそが「神道」であり、
つまり──神道とは、本来“多重信仰”“多元信仰”そのものだったのです。
つまり『純粋神道の回復』というスローガンは、歴史を回復するどころか、むしろ日本の伝統をゆがめてしまう危険をはらんでいるのです。
(本稿は、note掲載記事を増補・再構成したロング版です。元記事はこちら ➝ https://note.com/muratawisdom/n/n651c3bf8ae01 )